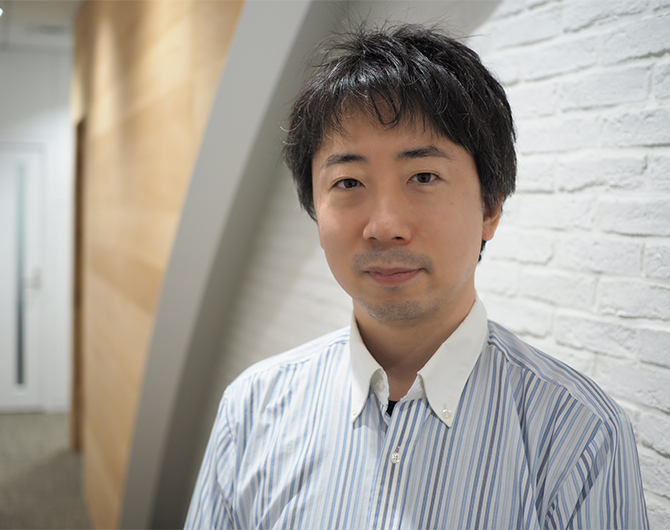
医師からエンジニアへ。リアルワールドデータで現場を変えるプロダクトを生み出す開発環境とは
医療機関支援部
羽山陽介
◆羽山さんについて
現在、どのような仕事をされているのでしょうか?
医療機関の中で医師やスタッフの方々が使用するアプリケーションの開発をしています。自ら手を動かして開発しながら、開発チームのメンバーのマネジメント業務も行っています。時には医療機関に訪問して現場のニーズや課題のヒアリングを行い、ニーズを開発案件に落とし込むこともよく行います。
現在、リアルワールドデータ株式会社でエンジニアとして活躍していますが、このキャリアに至るまで、どのような経緯、気持ちで歩んでこられたのでしょうか?
リアルワールドデータ株式会社は、京都大学薬剤疫学分野の教授が設立した会社で、京都大学への入学前からその会社を紹介され、オリエンテーションを受けました。リアルワールドのデータをプログラミング言語で「見える化」するというミッションを与えられ、これが自分に合っていたんです。プログラミングの経験はありませんでしたが元々あったシステムを改築する過程で力がついていきました。
医師の中でエンジニアとしても活躍される方はまだ多くはないという印象がありますが、エンジニアとしてもやっていこうと思われたきっかけを教えてください。
職業的には、医師でもエンジニアでも大きな違いはないと思っています。ただ、アナログが故に未解決の問題は医療現場にまだまだ多く、エンジニアとしてのスキルを磨けば解決策を提示できるのではないかと考えるようになりました。病院を訪問して「こういうことを解決したいと思いませんか?」「何か不足している点はありませんか?」と現場のニーズを聞くと、まだ多くの医師や看護師が手作業でデータを扱っていることがわかります。データをもっと簡単に扱えれば、業務が効率化できるはずです。1年ほどエンジニアとして関わる中で、実際にシステムを作り、「こんなシステムがあれば解決できますが、どうでしょうか?」と提案することで、病院の枠を超えた解決策に繋がるのではないかと考えるようになりました。
◆開発プロダクト「TidyMed」について
まずはじめに、どのような機能を医療機関に提供しているのかを教えてください。
私はもともと医師だったため、現場の医師たちが忙しくて手が回らない状況を改善したいという強いモチベーションがあり、デジタルの力を活用すれば業務が効率化できると考えていました。そのような思いで開発したTidyMedは、特にCRC(治験コーディネーター)の方々を対象にした治験業務支援アプリケーションです。同時に、医師など専門職の方々に対して、広範な臨床研究業務をデジタル化し、効率化することを目的としています。
医療機関向けの治験・臨床研究業務支援アプリケーションを構築するうえで、どのような苦労がありましたか?
最も苦労した点は、病院では多くの専門職の方々が業務に従事しているため、それぞれの職種ごとに異なる課題を理解することです。例えば、CRC(治験コーディネーター)や事務スタッフなど、それぞれが抱える課題を把握する必要があります。特に、スタッフ自身も気付いていない課題を掘り起こし、解決策を提案・調整するには、多くのコミュニケーションが必要です。
また、本アプリケーションは電子カルテに接続し、機微な医療情報を扱います。サービス提供の場が医療機関内という閉じた環境であることや、個人情報を厳格に管理しながら適切に動作するシステムを構築するには、細心の注意が必要です。
さらに、薬事申請に必要な情報を記録・保存する機能を備えており、ER/ES指針などの各ガイドラインに基づくシステムバリデーションの遵守が求められます。そのため、通常の開発と比べ、文書作成やその他の作業に多大な労力を要する点も、特徴的な難しさだと感じています。
TidyMedは今後5年間でどのように進化していくのでしょうか?
まずは、現在の主機能である治験・臨床研究の支援機能を徹底的に強化し、現場の満足度を向上させることが最優先です。これが大前提であり、まずは数年間、この取り組みに注力します。
一方で、診療データの分析やチェック機能は、現時点では限定的です。これらの機能には現場のニーズがあるものの、医療機関の予算上の制約により十分に普及していません。そのため、今後はこの分野の拡充にも取り組みます。
さらに、言語処理や生成AIなどの最新技術を、医療機関という閉じた環境にも導入したいと考えています。これにより、現場のスタッフに新しいソリューションを提供でき、事業としての成長も見込めます。
後半の数年間は、医療機関ならではの革新的なソリューションを生み出し、これまでにない価値を提供できるようにしたいと考えています。
将来的に、データ入力をすべてシステムで完結させることは可能だと考えていますか?
治験のデータ入力を完全に自動化することは難しいと考えています。人が入力した情報には、常に誤りが含まれる可能性があり、そのため、電子的に自動収集された情報をソースデータとして扱うには、規制要件上の懸念があり、検証のハードルも高いのです。ただし、最終的に現場のスタッフが目視チェックを行うことで対応できる段階までシステム化することは可能だと考えています。
一方で、臨床研究や診療の分析に関しては、システムが提示する情報の目的は気づきを与えることであり、必ずしも完璧である必要はないと考えています。医療現場において、デジタルでできることには限界がありますし、現場のスタッフは、データが提示されれば自ら判断し行動できる専門家だからです。本アプリケーションの役割は、人の業務を代行するのではなく、伴走することであり、専門性を脅かすものではありません。私たちは、現場のスタッフの能力を強化する方向を目指しています。
TidyMedにはどのような技術が使われていますか?またその技術を選択された理由は何ですか?
TidyMedはWebアプリケーションとして、HTML、CSS、JavaScriptなどの一般的なWeb技術を使用しています。サーバーサイドの主要言語にはPythonを採用しています。Pythonを採用した理由は、将来的な発展性と当時の人気の高まりでしたが、結果的に、現在主流となっている自然言語処理の多くのモジュールがPythonで提供されており、非常に相性の良い選択だったと感じています。
今後取り入れたい技術や注目している技術はありますか?また、その技術を使用してどのような機能を実現したいと考えられているのでしょうか?
例えば、患者を診療している際に、3か月に一度の検査が必要な場合、チャットボットに「この患者の前回の検査日は?」と尋ねると、適切な回答が得られるシステムなど、生成AIを活用したさまざまなアイデアが考えられます。
現在、生成AIは創発的な能力を持ち、推論分野における競争が激化しています。医療現場でも大きな影響を与えると考える人もいますが、しかし、医療機関のように外部通信に制限がある環境では、こうした技術の導入は現時点では難しいと感じています。まず、医療機関内のシステム環境が整備されなければ、患者の詳細な診療分析や提案を行う生成AIは実用化できません。
さらに、高価なソリューションでは医療機関に導入されにくい可能性があります。そのため、別の方法で収益化が可能なソリューションに先進技術を組み込むことで、より受け入れられやすくなると考えています。
羽山さんが考える、TidyMed開発の面白さや魅力、やりがいについてお聞かせください。
医療現場のニーズに応える機能を開発する際、医療分野以外の便利なツールやソリューションからヒントを得ることがよくあります。他業界で活用されているアイデアや機能を、医療機関向けに使いやすい形に落とし込む工夫が求められる点が、非常に面白いと感じています。
また、医療機関の電子カルテに蓄積された膨大なデータを活用するため、大規模データの処理に関する知識を深めることができます。使いやすさも非常に重要で、分かりやすいUI・UX設計が求められます。そのため、常に新たな課題に挑戦でき、飽きることがありません。
さらに、開発中の課題を解決するために、先進的な外部モジュールを活用し、新たな視点で開発を進めることも多くあります。学習は欠かせませんが、医療現場にはまだ普及していないソリューションを開発し、医療機関のユーザーに喜んでいただけたとき、大きなやりがいを感じます。
◆開発チームについて
TidyMedの開発チームはどのようなチームですか?また、リモートワークを主体とした開発を円滑に進めるために、どのような工夫をされていますか?
開発にはPythonを使用していますが、チーム内にPythonを主言語とするメンバーはほとんどいません。現在のチームは5名で構成されており、メンバーの主言語もJavaやC#など、それぞれ異なります。私自身も、もともとはRを主言語としていました。それでも皆、勉強しながら熱心に開発に取り組んでおり、向上心の高いチームだと感じています。
20代から30代の比較的若いメンバーが多く、新しい技術への抵抗が少ないため、新しいパッケージやモジュールを積極的に選定・導入し、「これを使えばこのような価値を提供できるのでは?」と活発に議論を交わせるチームです。
リモートワークでは、一人で作業することで集中しづらく、生産性が低下する人もいます。また、コミュニケーションが減ると、一人で行き詰まることもあります。そのため、現状では午前と午後の2回、リモートでも開発時間を共有し、画面越しに顔を合わせて気軽に相談できる環境づくりを心がけています。また、座りっぱなしは健康によくないため、たまには出社することを勧めています(笑)。
医療業界や医療のバックグラウンドがないエンジニアの方でも、御社で共に活躍できるイメージはありますか?また、そうした方々と一緒に何か取り組む可能性はありますか?
ノンメディカルの方々とのセッションは非常に重要だと思っています。病院では患者さんの治療が最優先ですが、企業では収益が最も重要なため、発想が全く違います。ノンメディカルの方々は「これが会社にとってメリットになるか、ビジネスになるか」という視点で物事を捉え、外部環境の分析もしてくれるので医師にはない視点で非常に視野が広がります。彼らとのコミュニケーションを通じて、全く異なる発想を得たり、新しい解決策を見つけることができるので、とても刺激になります。一方で、私は医師として病院の内情をよく知っていますが、意外にも病院はデジタルに強くありません。エンジニアやノンメディカルの方が持っている「医師なら簡単にできるはず」というイメージは、実際とは大きく異なります。むしろ、病院内にはまだアナログな部分が多く、そこに未開拓のチャンスがあると感じています。「ここがブルーオーシャンじゃないですか」という提案をしながら開発をするという橋渡し役となって、デジタル化を進めることができるのはとても面白いと感じています。
医療のバックグラウンドはなく、エンジニアとして初めてメディカル領域に挑戦したい方々へのアドバイスはありますか?
JMDCグループやリアルワールドデータ株式会社には、初めてチャレンジするのに適した環境が整っています。例えば得意な言語が異なるなどがあったとしても、異なる分野の知見が融合する新しい場所になればいいと思います。JMDCグループやリアルワールドデータ社にはこれまでに蓄積されたデータやノウハウが豊富にあるので、おすすめできる環境だと思います。
どんな人に開発チームに入ってもらいたいですか?
先ほどお話しした通り、プログラミング言語の壁はありません。PythonやWebアプリ開発を一からでも勉強したいというモチベーションを持っている方は大歓迎です。
リモートワークがメインなので、交流の機会が減ってしまう職場環境でも、困ったときに人に頼ることができて、また協調性を失わないコミュニケーション能力が求められます。
新しいものを導入することも積極的に行っており、異分野の情報や技術の進歩を取り入れることに抵抗がない人の方が、楽しく仕事ができると思います。同じことをずっと続けるのが好きな人には向かないかもしれませんが、新しいソリューションを取り入れて、より良い価値を生み出すことを考えられる人の方が相性が良いように思います。新しいものが好きで、世の中の役に立つものづくりをしたい人にとっては、とても良い環境だと思います。

